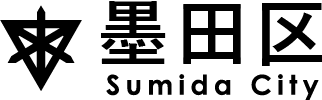令和元年(2019年)以降、高齢者人口は微減傾向で、令和5年(2023年)では5万9,941人となっています。高齢者人口を65歳から74歳までの前期高齢者と75歳以上の後期高齢者に区分すると、後期高齢者の増加が目立ちます。今後、高齢者人口は数年間ほぼ横ばいで推移することが見込まれているものの、団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年(2040年)、さらに同世代が75歳以上となる令和32年(2050年)に向けて増加が見込まれます。
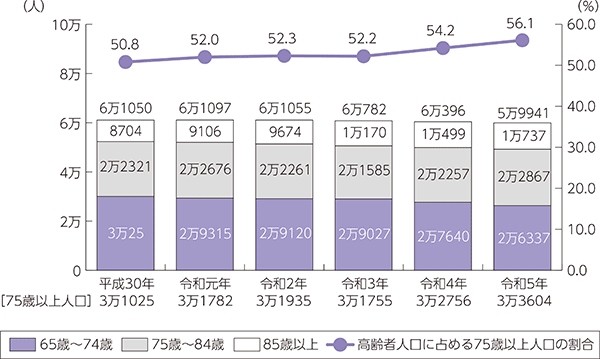
[資料]墨田区住民基本台帳(各年10月1日)
高齢者のいる一般世帯数は年々増加しており、令和2年(2020年)では4万2,521世帯となっています。このうち、高齢単身世帯数が1万7,478世帯、高齢夫婦世帯数が1万326世帯となっており、とりわけ高齢単身世帯が増加しています。
単位(世帯)
| 区分 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 |
|---|---|---|---|---|
| 高齢者のいる一般世帯数 | 3万3,716 | 3万7,565 | 4万1,161 | 4万2,521 |
| 高齢単身世帯数 | 1万626 | 1万2,590 | 1万5,257 | 1万7,478 |
| 高齢夫婦世帯数 | 8,663 | 9,230 | 1万141 | 1万326 |
| その他の世帯数 | 1万4,427 | 1万5,745 | 1万5,763 | 1万4,717 |
| 高齢者のいる一般世帯数に占める高齢単身世帯数の割合 | 31.5パーセント | 33.5パーセント | 37.1パーセント | 41.1パーセント |
[資料]総務省「国勢調査報告」
要支援・要介護認定者数は増加しており、令和5年(2023年)9月末現在で1万2,605人となっています。また、令和6年(2024年)から令和32年(2050年)の要支援・要介護認定者数の見込みを見ると、その総数は年々増加し、令和22年(2040年)で1万5,057人となっています。令和6年(2024年)から令和22年(2040年)にかけて特に要介護3以上の伸び率が高くなっています。
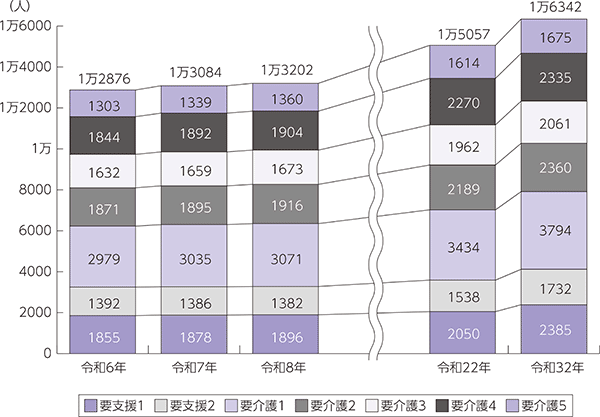
[資料]地域包括ケア「見える化」システムにより算出(各年9月末)
令和4年度の職員の過不足の状況は、「充足している」が37.3パーセントであるのに対し、「やや不足」「不足」と「大いに不足」と回答した事業所を合わせた“不足”が59.9パーセントで、そのうち「大いに不足」が5.2パーセントとなっています。
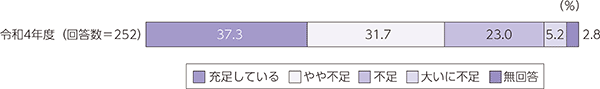
[資料]墨田区「令和4年度墨田区介護サービス事業所調査報告書」(令和4年12月)
本計画は、高齢者を取り巻く様々な課題に的確に対応し、高齢者が住み慣れた地域で自分らしくいきいきと暮らせる社会を実現するため、取り組むべき施策を明らかにすることを目的としています。区では、高齢者福祉施策の総合的な展開を図るとともに、介護保険制度の円滑な運営や地域包括ケアシステムを充実させることで、この社会の実現をめざします。
本計画の策定に当たっては、公募した区民や学識経験者などから構成される「墨田区介護保険事業運営協議会」等で協議・検討しています。また、庁内でも「第8期計画」の進捗状況や課題を分析するため、ワーキンググループを設置し、分野ごとの課題や解決策を検討しています。
さらに、計画策定に先立ち「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」「在宅介護実態調査」等の調査を実施し、高齢者や介護者の生活実態の把握に努め、高齢者福祉施策および介護サービスの在り方を検討しています。
区では、高齢者福祉総合計画・第6期介護保険事業計画から、「みどり」「同愛」「なりひら」「こうめ」「むこうじま」「うめわか」「ぶんか」「八広はなみずき」の8つの圏域ごとの「地域包括ケアシステム」実現をめざすために、日常生活圏域別地域包括ケア計画(以下「地域包括ケア計画」)を策定しています。
他の自治体と比較し、区の地域包括ケア計画の特徴と言える点が、次のとおり3点あります。
(1)高齢者福祉総合計画・第9期介護保険事業計画(以下「第9期計画」)に地域包括ケア計画を章立てして掲載するとともに、8つの圏域ごとに分冊を作成します。
(2)町会・自治会、民生委員・児童委員、見守り協力員、介護サービス事業者、医療関係者等の地域で活躍されている方々で構成されている地域ケア会議により、圏域ごとの住民・関係者の声を十分に取り入れています。
(3)地域ケア会議での意見交換を踏まえ、圏域ごとの現況や課題を明らかにし、さらに、「第9期計画」における地域包括ケアシステムの充実に向けた5つの「めざすべき姿」のいずれかにつながる重点的な取組を設定しています。
このように、区では「第9期計画」とともに、地域包括ケア計画を一体的に策定し、すみだらしい、地域で顔の見えるつながりの中で、高齢者が生きがいをもって生活できる地域づくりを進めます。
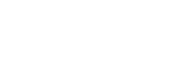
 Close
Close