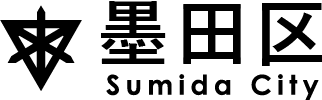9月の番組表

キャスター 大山 美佳さん
毎日、午前9時、正午、午後4時・8時から地上デジタル11チャンネルで放送しています(各15分間)。なお、放送終了後は区HPでご覧になれます。
[問合せ]広報広聴担当 電話:03-5608-6220
| 放映日 | 午前9時 | 正午 | 午後4時 | 午後8時 |
|---|---|---|---|---|
| 9月7日(日曜日)から13日(土曜日)まで | [すみだのそこが知りたい]友好都市「鹿沼市」 | [すみだのそこが知りたい]友好都市「鹿沼市」 | [すみだのそこが知りたい]友好都市「鹿沼市」 | [すみだのそこが知りたい]友好都市「鹿沼市」 |
| 9月14日(日曜日)から20日(土曜日)まで | [特集]墨田区名誉区民 五街道 雲助(再放送) | [すみだのそこが知りたい]友好都市「鹿沼市」 | [特集]墨田区名誉区民 五街道 雲助(再放送) | [すみだのそこが知りたい]友好都市「鹿沼市」 |
| 9月21日(日曜日)から27日(土曜日)まで | [くまだまさしを1日貸しちゃいます!]レイクランド大学 | [くまだまさしを1日貸しちゃいます!]レイクランド大学 | [くまだまさしを1日貸しちゃいます!]レイクランド大学 | [くまだまさしを1日貸しちゃいます!]レイクランド大学 |
| 9月28日(日曜日)から10月4日(土曜日)まで | [くまだまさしを1日貸しちゃいます!]レイクランド大学 | [特集]墨田区名誉区民 五街道 雲助(再放送) | [くまだまさしを1日貸しちゃいます!]レイクランド大学 | [特集]墨田区名誉区民 五街道 雲助(再放送) |
*内容が一部変更になる場合あり
*ケーブルテレビへの加入・問合せは、J:COMカスタマーセンター 電話:0120-999-000へ
このページは広報広聴担当が担当しています。
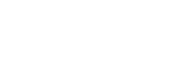
 Close
Close