ページID:440993512
更新日:2024年11月22日
100年の歴史を紡いできました
民生委員のはじまりは、大正6年5月に岡山県に誕生した「済世顧問」制度にあるといわれています。
大正天皇から県民の生活状況について質問を受けた笠井県知事が、県民の生活実態を調査した上で、この制度を創設したのです。
以下、墨田区に関する民生委員の歴史・記録について、振り返ります。
大正
大正7年(1918)6月
東京では、防貧事業に積極的な井上友一府知事 が、渋沢栄一らの協力を得て「救済委員」を置く。
同年10月
都市における失業者や貧困者が大きな社会問題となる中、この制度が全国へ広がる。
大正9年(1920)12月
東京では「救済委員」制度を「方面委員」に改称。その後この名称が全国的に広がる。

渋沢栄一

社会福祉の先駆者 留岡幸助と渋沢栄一
昭和
昭和4年(1929)
方面委員は、救護を行う市町村長の補助機関として位置づけられる。(救護法の公布)
昭和11年(1936)
初めて国の制度として、統一基準が設けられ全国制度となる。東京では昭和18年の都制施行により3,540人が委嘱される。
戦後の苦難の時代を経て、経済成長とともに各種制度が整備され、委員活動が広がる。
昭和21年(1946)
民生委員令公布、都道府県知事から厚生大臣委嘱となる。
同年「生活保護法」公布。

昭和38年11月 民生委員集合写真

昭和40年~昭和50年 民生委員全体会

昭和51年 第7地区の民生委員協議会
昭和44年(1969)
多様化する福祉課題の研究を深める場として「都民連」を設置。
児童・障がい・低所得・老人の4分野と婦人部会を設ける。
昭和55年(1980)
児童委員と児童相談所の二者から連携が始まり、現在の地区連絡協議会(四者協)として運営される。

昭和40年~昭和50年 訪問調査
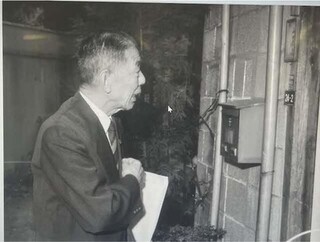
昭和40年~昭和50年 訪問調査
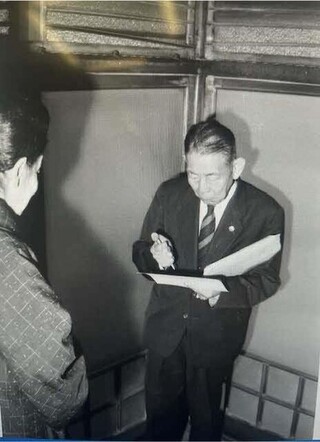
昭和40年~昭和50年 訪問調査
平成
平成6年(1994)
児童委員への期待が高まる一方、その活動の低迷が指摘される中、「主任児童委員」が設置される。
平成23年(2011)
東日本大震災発生
平成28年(2016)
制度創設100周年記念事業の展開
令和
令和2年~令和4年(2020~2022)
コロナ感染症が世界的に大流行。会議は書面やオンラインへ 。

令和4年 「墨田区のお知らせ」より 各地区の会長と主任児童委員部会長

令和6年 民生委員正副会長会
お問い合わせ
このページは地域福祉課が担当しています。
