ページID:988161605
更新日:2020年5月19日
すみだ郷土文化資料館では、開館10周年時に特別展「隅田川文化の誕生-梅若伝説と幻の町・隅田宿ー」を開催したことを踏まえ、隅田川花火大会に合わせて毎年展示していた花火関係資料を一堂に集め、以下のとおり開館20周年記念特別展を実施しました。
開館20周年記念特別展「隅田川花火の三九〇年」
展示概要
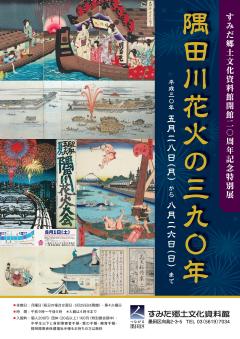
毎年、7月の最終土曜日におこなわれる隅田川花火大会。歴史的史料では、天正17年(1589)のちの仙台藩主伊達政宗、ついで慶長18年(1613)徳川家康が観賞したのが、日本における花火の始まりである。そして、江戸幕府にも大きな影響力を持つ僧・天海が寛永5年(1628)に浅草寺に来た際に花火を上げてもてなしたのが、隅田川
での花火の最初となる。このように、日本での花火にはおよそ430年の歴史があり、そのほとんどが隅田川での花火の歴史と重なることから、日本花火の歴史的発展は、隅田川花火のそれと重なるといっても過言ではない。
当館は開館以来、隅田川花火に関する浮世絵や技術書を中心に資料収集に努めており、特に技術書は国内でも有数のコレクションを擁している。また、毎年の調査研究の成果により、江戸時代初期から390年続く隅田川花火の歴史がおおむね明らかになってきた。
開館10周年時に特別展「隅田川文化の誕生―梅若伝説と幻の町・隅田宿―」を行ったことを踏まえ、開館20周年に毎年隅田川花火大会に合わせて展示していた花火関係資料を一同に集め、特別展として実施することにした。
事業概要
- 隅田川花火に関するさらなる資料発掘・調査研究:平成29年、30年の2年計画で東北大学附属図書館など館外出張による調査研究を実施(研究紀要第4号にて調査報告を掲載)
 展示図録の作成:4色200頁、1200円(税込)で頒布
展示図録の作成:4色200頁、1200円(税込)で頒布- 印刷物:ポスター、チラシ、「みやこどり」(パンフレット:8頁)
- 内覧会の実施:5月27日午後に展示協力者、報道関係者などを招待
- 入館料:200円(開館10周年特別展と同様)
- 花火映像のスクリーンでの上映:2階ジオラマを閉鎖してスクリーンを設置し、昭和11年両国川開大花火の映像を上映
- 実物資料(筒・花火玉)の展示:長野市立博物館から花火筒、打ち上げ玉(模型)を借用・展示
- 講演会の実施【附属事業】:3回実施
- ノベルティの作成【附属事業】:クリアホルダー3種(すみだ郷土文化資料館ボランティアの会による製作協力)
展示構成
第1章 隅田川花火のはじまり
第2章 船遊びと中洲花火
第3章 打上花火と川開大花火
第4章 隅田川の夕涼文化
第5章 料亭文化と両国広小路
第6章 子供花火からおもちゃ花火へ
第7章 武士の狼煙と花火
第8章 明治の花火
第9章 大正・昭和の発展
第10章 戦後の復活・中断から現在へ
エピローグ 全国の花火との交流
以下、第1章~第3章を2階展示室A、第4章~第7章を同B、第8章~エピローグを3階展示室に配置した。
会期
平成30年5月28日(月曜日)から8月26日(日曜日)まで
展示関連講座を開催しました
- 7月1日(日曜日)「南信州の煙火」講師:飯田市美術博物館学芸員 櫻井 弘人 氏
- 7月8日(日曜日)「昭和の隅田川花火」講師:公益財団法人日本煙火協会専務理事 河野 晴行 氏
- 7月22日(日曜日)「明治・大正期の隅田川花火」講師:当館学芸員 福澤 徹三 氏
明治一五〇年記念企画展「水神社の世界-失われた景観と源頼朝伝説ー」
展示概要
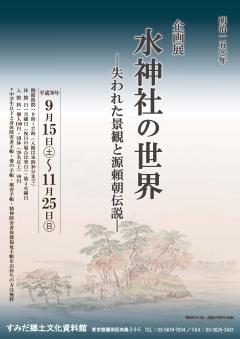
およそ800年前の墨田区墨堤付近には、隅田宿という中世の宿がありました。隅田宿には古代東海道が横断しており、中世になると鎌倉街道下道が縦断して官道の交差する場となります。また、15世紀の軍記物などには西国からの水運を迎え入れる玄関口として描かれており、水陸交通の要衝として栄えました。現在の白鬚橋上流付近は、中世隅田川の渡河点と考えられており、そのためこの地域には、源頼朝の渡河伝説や太田道灌による架橋伝説が残されています。
水神社は、この隅田宿空間内に創建されたと伝えられます。明治になると矢掛弓雄という神主の来着によって隅田川神社として再編されますが、近代以前の向島地域と寺社に関するものや隅田川と源頼朝伝説にまつわる貴重な資料が数多く伝来しています。墨田区の文化財係では、平成27年以降から、これら隅田川神社所蔵資料の文化財登録を目指した調査研究を行ってきています。本展示では、この隅田川神社所蔵資料を中心に、隅田宿の中世的景観を探るとともに、水神社から隅田川神社への転換の歴史を紹介しました。
会期
平成30年9月15日(土曜日)から11月25日(日曜日)まで
展示関連講座を開催しました
- 10月13日(土曜日)「隅田川神社資料と矢掛弓雄」 講師:法政大学非常勤講師 中山 学 氏
- 10月28日(日曜日)「隅田川神社所蔵「伝頼朝橋の鎹」をめぐってー隅田川と中世の橋ー」 講師:専修大学准教授 田中 禎昭 氏
企画展「東京大空襲-罹災者・救護者・戦争遺跡ー」
展示概要
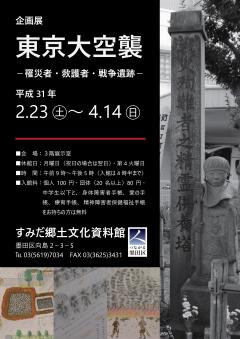
平成31年は、1945(昭和20)年3月10日の東京大空襲から74年目にあたります。
今回は、3つの視点で空襲を示しました。
罹災者については、体験者から聞き取った避難の軌跡を展示しました。今後、体験記を読み込むヒントとなるものです。これまでの共同研究で制作した「東京大空襲 いのちの被災地図」も展示し、実際の避難の軌跡との違いも示しました。
救護者では、軍隊の役割に注目し、遺体回収に従事した陸海軍の兵士の証言や軍の資料から焼け跡整理の命令を展示しました。遺体回収は空襲体験画にも描かれ、絵を描いた体験者の中には、1970年代に空襲体験記を『東京大空襲・戦災誌』に寄稿した人がいることも紹介しました。
また、空襲後の避難所の位置と、軍が開いた救護所の場所を地図化し、救護に当たった人々の手記を展示しました。そこでは、731部隊の部隊長として知られる石井四郎の開発した、石井式濾水機が隅田川で使われた証言があり、関連資料と併せて展示しました。
戦争遺跡では、これまでまとめてきた空襲によるものだけでなく、近代の戦争に関わるものも初めて取り上げ、所在図と写真を中心に紹介しました。
会期
平成31年2月23日(土曜日)から4月14日(日曜日)まで
お問い合わせ
このページはすみだ郷土文化資料館が担当しています。
