ページID:881773031
更新日:2024年7月11日
令和5年度は、以下の特集展示等を開催しました。
特集展示 「すみだの和歌と漢詩」
展示概要
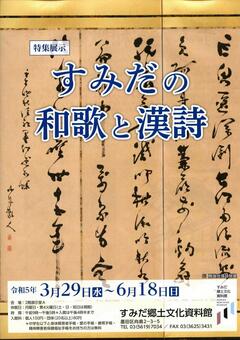
墨田区の歌の歴史は、はるか昔、在原業平が平安時代前期に京都から東下の旅の途中、隅田川で都鳥に託して京を偲ぶ一首を作ったことに始まります。名所としての地位は、建保名所百首(建保3年〈1215〉成立)によって固まり、京の公家達は遙か東国の隅田川に思いを馳せて、多くの和歌を詠みました。
そんな名所に大きな変化が訪れたのが江戸時代でした。徳川家康が江戸に入り、天下人としての地位を固めて行くにつれて、京都の公家の江戸下向が盛んになりました。慶長12年(1607)梅若寺に近衛信尹が立ち寄り、梅を上下に分け木母寺と称するようになったことは周知のことでしょう。江戸にも和歌文化が根ざし、身近な名所として武士・町人・百姓たちも広く詠むようになりました。
一方江戸時代には漢詩も盛んになりました。特に儒学者荻生徂徠の高弟たちは、漢学文献に精通するという理由で徂徠が漢詩作りを否定しなかったため、多く作るようになり、江戸時代中後期の漢詩ブームが起こります。隅田川は「墨水三絶」と呼ばれる著名詩の舞台ともなりました。勝海舟も隅田川の漢詩を詠んでいます。今回の特集展示では、隅田川にちなんだ和歌と漢詩を紹介しました。
会期
令和5年3月29日(水曜日)から6月18日(日曜日)まで
特集展「伝統工芸展-すみだ粋の世界-」
展示概要
すみだは「モノづくりのまち」と言われますが、北部(向島地区)と南部(本所地区)で特徴が異なります。江戸時代までの北部は、わずかな森と竹薮以外はほとんどが農村地帯でした。業平周辺は江戸で使う瓦の大量生産地区だったため瓦職人が多く、村の生活を支える鍛冶職人や鋳物職人、木地職人、周辺の川を活かした染織職人の他、宮大工や神輿職人、錺金具職人といった多数の寺社を有する地域ならではの仕事も見られました。一方、南部は、江戸時代の開発により早くから市街地として発展し、町人や武士が使う道具類が多く作られました。また、芝居小屋や飲食店で賑わう両国界隈には観光客や参詣客のための土産物や装飾品、料亭で使われる三味線や琴、着物類に関わる職人、周辺の寺社を支える仏具職人が見られ、釣道具屋、ろうそく問屋、紙問屋など、多様な店があったようです。
本展では、「堂宮彫刻」「表具(表装仕立て)」「押絵羽子板」「西洋剃刀」「べっ甲細工」「組紐」「和船製造」「足袋」「墨壺」を中心に、長きにわたりモノづくりに携わり、墨田区の「登録無形文化財技術保持者」としても技術と文化の伝承に貢献して来られた職人の方々とその作品をご紹介しました。
会期
令和5年7月1日(土曜日)から9月24日(日曜日)まで
特集展示「コドモの世界―江戸東京のあそびとまなびー」
展示概要
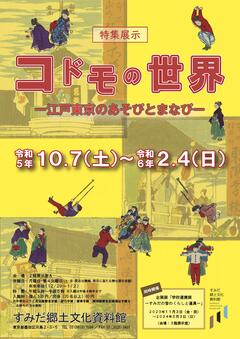
当館では、令和5年度の博学連携事業の一環として、3階展示室にて「すみだの昔のくらしと道具」を開催し、区内小学校からの展示見学受け入れを行いました。
ひとくちに「昔のくらし」といっても、年齢や性別、身分など、その対象によってさまざまです。現代社会のなかでは、多くの子どもの暮らしは学校生活が基準になっているのではないでしょうか。現在のように、「学ぶ権利」をすべての子どもに与える動きは、明治5年(1872)に発布された学制が契機となっています。しかし、前近代の子どもたちは、労働力として期待されることも多かったため、生まれた階層などによって学びのかたちは大きく異なっていました。江戸時代になると、いまに引き継がれる「子宝」としての考え方が生まれ、子どもの生活も大きく変化します。
本展示では、江戸東京の子どもの暮らしや、彼らの学びと遊びの風景や道具、教材の変遷について、おもちゃ絵や双六など館蔵の浮世絵のほか、泥めんこや人形、ミニチュアなどの埋蔵文化財を通じて紹介しました。
会期
令和5年10月7日(土曜日)から令和6年2月4日(日曜日)まで
特集展示「ひなまつり-旧家に伝わるおひなさま-」
展示概要
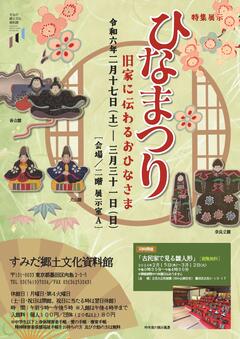
ひなまつりの起源は3月の「上巳の節句」とされています。身の穢れをヒトガタに託して水に流す祓えの行事に、貴族の子女の間で平安時代から行われていた「ひいな遊び」が習合して3月3日に人形を飾り、供物をささげ、女児の健やかな成長を願う年中行事となっていったと考えられています。
江戸時代中期には、現在の雛人形の原型となる豪華な衣装を着た「座雛」が誕生し、後期には、人形とともに飾る雛道具も様々な種類が作られるようになりました。幕末期には、雛段に男雛女雛やお供の人形と様々な雛道具を飾りつける七段の飾りがほぼ完成しました。
すみだ郷土文化資料館には、区民の方や区にゆかりの深い方からご寄贈・ご寄託いただいた雛人形が所蔵されています。いずれも、子の誕生を祝い、成長を願って各家で大切に飾られ、代々伝えられてきたものです。度重なる震災や空襲、水害などで戦前の資料の多くが失われてしまったため、現存している雛人形は当時の人々の想いを垣間見ることのできる貴重な資料なのです。本展では、墨田ゆかりの旧家に伝わってきた歴史的にも美術的にも価値の高い雛人形と合わせて、全国の雛人形を描いた大正時代の図譜『雛百種』を紹介しました。
会期
令和6年2月17日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日まで)
常設展示
隅田川レガッタ展
かつての大学対抗戦等で使用されたオールや艇庫の模型など、隅田川レガッタに関する資料の展示
会期
令和5年3月29日(水曜日)から7月2日(日曜日)まで
東京空襲体験画展
東京空襲の体験者が自らの体験を描いた絵画の展示
会期
令和5年7月15日(土曜日)から
お問い合わせ
このページはすみだ郷土文化資料館が担当しています。
