ページID:898298670
更新日:2007年2月20日
開催期間:平成11年2月27日(土曜日)から平成11年3月22日(月曜日)まで
かつてすみだには、寺島村、柳島村という二つの村がありました。
江戸時代以来の名所というと、桜の墨堤、百花園、柳島妙見などが浮かんできますが、実は、こうした著名な場所はこれら二つの村の中にあったのです。
では、名所として賑わう村の中で、人々はどんなくらしを営んでいたのでしょうか?
この企画展では、区民の方々から寄贈していただいた昔の道具類のほか、寺島や柳島を描いた錦絵・絵図などを紹介し、隅田川に育まれた二つの村の、江戸時代から伝わる伝統的なくらしと文化を再現しました。
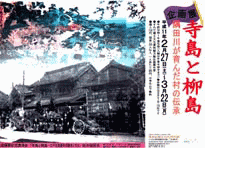
寺島村
東向島は、昭和39年から40年まで(1964年から1965年まで)の町名改正以前には寺島と呼ばれていました。
地名の由来は、「蓮花寺の縁起に彼寺は鎌倉の執権武蔵守経時鎌倉郡佐介谷に建立したりしを、息頼助弘長元年ここに引移し自ら中興開山となれり、これ村名の起れる所なり、又法泉寺の伝によれば、此寺は葛西三郎清重が開基にして村内大抵かの寺の境内なりし故この村名あり」(「新編武蔵風土記稿」)と、いずれにしても寺の存在が村名につながったと考えられます。
すでに、応永5年(1398年)の「葛西御厨田数注文写」にその名が見え、中世から村落が形成されていたことがうかがえます。近世以降は、葛飾郡西葛西領に属し、その多くが多賀氏の知行地であり、「元禄郷帳」によれば村高は621石余でした。多賀氏が絶えた後は、幕府領として幕末に至っています。
この地一帯は、江戸近郊の名所として多くの人々でにぎわうとともに、消費都市江戸の台所をまかなう近郊農村として、生鮮野菜の供給地としても知られていました。享保期に著された「続江戸砂子温故名跡志」には「寺島茄子」の産地として、寺島材の名も紹介されています。
明治に入って南葛飾郡寺島村および大木村・吾嬬村の大字となり、大字寺島の内に南・北居村、新田、水道向など12の小字に分かれていましたが、大正12年(1923年)に寺島村・須崎村・中ノ郷村など7ケ村の一部を合併して、寺島町となり、昭和7年(1932年)東京市の市域拡張により、向島区が成立しました。
柳島村
柳島という地名は近世以前の文献には確認できないのですが、「葛西志」によると、現在の墨田区の東南に位置する広域をさしていたようです。また、地名の由来は「柳の木が多かったため」、と記されていますが詳らかではありません。
江戸時代には武蔵国葛飾郡葛西領となり、その村域は万治年間(1658年から1661年まで)に始まった本所開拓により、南は深川六間堀代地町に至り、北は北十間川に沿い、東は横十間川を越えて亀戸村に接していました。また、西に隅田川、東に中川が流れる墨田区の東南に位置する柳島村は、この二つの川をつなぐ北十間川や、横十間川・大横川に三方を囲まれ、水運に恵まれた地域でした。
柳島妙見と親しまれ、安藤広重の「江戸名所四十八景」の一つにもなっている法性寺や、萩の名所として名高く萩寺ともよばれていた龍眼寺(現・江東区亀戸3丁目)などが知られています。亀戸天神社や梅屋敷など寺社や名所が数多く見られた隣の亀戸村とともに、北十間川や横十間川といった水運を利用した江戸近郊の遊覧の地でもありました。
明治時代に至り、明治21年(1888年)市制町村制が公布され、翌年、東京市が成立しました。この施行に伴い東京府下の区町村の区域名称変更が行われ、本所区は南葛飾郡から須崎・押上・小梅・請地・中ノ郷・柳島の各村の大部分を受け入れ、本所亀戸町・松代町四丁目などは南葛飾郡亀戸村に移されることとなりまし。この際、柳島村を南北に通過している横十間川が本所区と南葛飾郡亀戸村の境となったのです。
寺島と柳島の旧家
今回の企画展示では、寺島と柳島の旧家、特に寺島の松本家と柳島の大澤家の伝承に注目し、区民の皆さんから寄贈していただいた民具や錦絵、絵図などさまざまな資料の助けを借りながら、二つの村の伝統的なくらしの再現を試みることにいたしました。
松本家・大澤家という二つの家に焦点を絞ったのは、江戸時代以来、両家が村の中核的な地主として多数の古文書、民具、生活習慣をまとまった形で伝承し、古い時代の家の暮らしの全体像を復原することが可能であり、それを通して寺島・柳島に所在した旧村落の生活の実態にも接近できると考えたからです。
お問い合わせ
このページはすみだ郷土文化資料館が担当しています。
