ページID:947436286
更新日:2005年3月21日
大野 勘三郎(おおの かんざぶろう)
堂宮彫刻(どうみやちょうこく)は、神社仏閣を飾る欄間(らんま)や木鼻(きばな)などの木彫刻をいいます。
その起源は16世紀、欄間彫刻の盛行に伴い大工(ばんしょう番匠)から分化して成立した「木彫り師」「宮彫り師」にたどることができます。江戸時代以後、墨田区周辺には神社仏閣が多く建てられ、また隅田川の水運による木材の供給の便もあり、仏師や彫師などが隅田川周辺に多く居住するようになりました。大野勘三郎さんの堂宮彫刻は、こうした条件の下で育まれた地域性豊かな伝統技術です。
大野さんは、大正4年栃木県に生まれました。昭和5年、向島在住の宮彫り師・後藤桂林氏の下で修行し、桂林氏の死後師匠宅で開業しました。関東地方の木彫り師には、後藤流、石川流、島村流などの伝統的流派がありますが、大野さんは後藤流の最後の後継者でもあります。
欄間「松に雉子」(部分)

(すみだ郷土文化資料館蔵)
観音
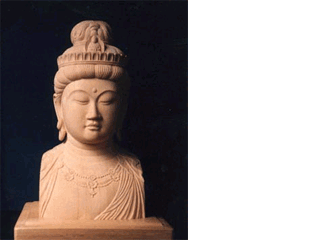
(個人蔵)
お問い合わせ
このページは地域教育支援課が担当しています。
